本屋さんの特等席、お客さんからよく見える平置きの書台や壁越しの面陳を埋め尽くす、毎月のように刊行される新書シリーズ。
一時期のブームからは少し鎮静化したようですが、それでも数多くの出版社から様々なテーマを掲げた作品が毎月、大量に送り出されています。本屋さんにとっても新刊という名の書棚のラインナップ新陳代謝を維持するためにはもはや欠かせない存在となった新書ですが、その中でも古参中の古参とされる岩波新書。
他の新書シリーズに対してやや古典的(エバーグリーン)なテーマであったり、特定の指向性のある読者層に向けた、強い問題提起を含む作品が多くラインナップされているかと思います。
今回ご紹介する本も、かなり強いテーマ性と問題提起を掲げた一冊。
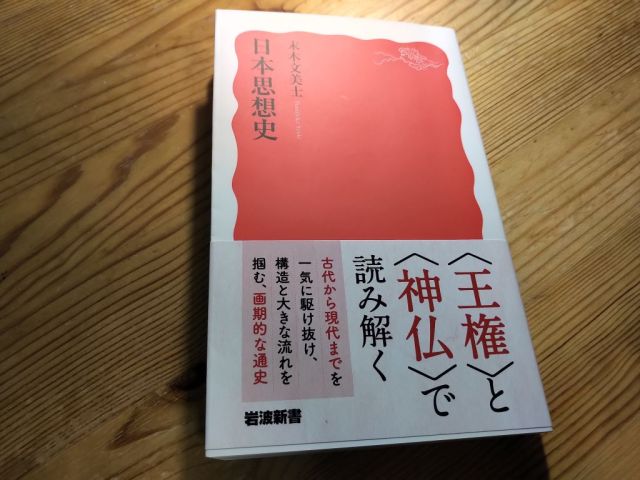 「日本思想史」(末木文美士 岩波新書)をご紹介します。
「日本思想史」(末木文美士 岩波新書)をご紹介します。
著者は東京大学に所属された(現在は名誉教授)著名な古代、中世の仏教研究者で、比較的穏当な筆致で中華世界へ請来する以前の仏典から日本に導入された仏教の定着、日本におけるローカライズされる姿までを宗派に拘ることなく通史として描くことができる稀有な方。その通史としての筆致も平板なものではなく、日本仏教の特異点や宗派、宗祖に拘る著述や議論に対して敢然と疑問を投じつつ、冷静に通史の中にそれらを位置づけていく、一般書籍としては貴重な、宗派に囚われない日本の宗教史を描ける方です。
そのような碩学が敢えて冒頭に刻み込んだ言葉に衝撃が走ります。曰く、
「最新流行の欧米の概念を使って、その口真似のうまい学者が思想家としてもてはやされた」
「思想や哲学は一部の好事家の愛好品か、流行を追うファッションで十分であり、そんなことには関係なく、国も社会も動いてきた」
本屋さんに大量に積み上げられる、ビジネスマンに向けた思想や哲学に類する書籍のなんと多いこと、その内容の殆どが西洋哲学のいいところ取り的な著述である点に大きな疑問を持っていた私にとっては非常に腑に落ちる一文ではあったのですが、それ故に本書の内容に大きな不安を抱いたこともまた事実です(僅か3ページほどですが、驚愕の「はじめに」は是非ご一読で(立ち読みでもいいかな、と))。
日本で思想、哲学を扱う研究者、出版、マスコミ関係の方々すべてを敵に回すような強烈な巻頭辞に対して、果たして本書の内容が応えているのか、更には著者が敢えて新書というフォーマットの特性を用いて表現するという内容に危うさを感じつつも、非常に興味を持って読み始めました。
私自身は思想も哲学も論じるに足りる知見を持ち合わせていませんので、あくまでも単なる本読みとしての感想ですが、流石に200ページ少々で思想史概論から始まり、古代から東日本大震災までの時間軸を通史として綴るには絶対的に分量が不足しており、表題にある内容を本書だけで満たすことは全くできません。特に初学者にとってはコンパクトすぎる記述を単純化して捉えてしまう恐れがあり、全く勧めることはできません。
むしろかなりの程度、日本史についての知識を有されている方が読まれることを当然として綴られたと思われる省力化された筆致。表面的にその内容は、文学、思想、宗教面でポイントとなる事項、人物を極端に圧縮した日本史通史にキーワードとして添えていくという体裁かと思います。
著者が得意とする通史を超特急で綴る本書、しかしながら著者のこれまで数多く手がけてきた通史のスタイルと少し様相が異なります。これまでの著作では主に中世まで、特に平安から鎌倉時代の著述に重点を置く著作が多かったと思いますが、本書では全体の半数以上を江戸時代以降の内容を描くことに充てていきます。多くの日本の思想史を綴る著作においても同じように、それ以前の歴史上で思想史を描き込むための前提となる内容が極めて限られるために致し方ないところかとは思いますが、冒頭の著者の言葉を享けて読み始めると、分量以上に江戸時代以前の内容には物足りなさを感じることも事実です。
そして、著者が本書を手掛ける大きな理由であり、特徴的な内容と思われるのが、超特急で綴られる日本史通史の文末に忍ばせる、仏教史としての視点、仏教が日本の思想に与えた影響が余りにも軽視されていることへの憤り。
著者の著述における特徴かと思いますが、通り一辺倒に読んでしまうと前述のように日本史の通史に添えた、単なる思想関係のキーワード集にも捉えられてしまうのですが、文末にぽつりと語られる内容こそが重要なポイント。新書というフォーマットの限界を超えるために著者が用意した仕掛けを注意深く確認することが求められます。
このような著述を採られているため、各論に関する著述においては、神話の成立や集積過程の論述に見えるように「重要ではない」とばっさり切り捨ててしまう部分が認められる一方、宗教的な視点でその後の歴史における思想面で多大な影響を与える部分については、相応に記述を割いていきます。
まず、国家神道に至る道筋では、その前時代から神道がひとつの信仰の形態として整備されていく過程を要所できっちり繋がるように指摘を入れていきます。儒教に関しても、神道、国学の相互関係と教育勅語、帝国憲法に繋がる過程の連動性にも配慮を示していきます(小中華論を含めて)が、その一方で日本において仏教のような定着を見せなかった結果、特に民衆にとっての思想、宗教としての影響は限定的であったことを明確に示していきます。その上で、著者が最も述べたいと願う仏教の思想面での影響。神道が信仰としての体系を整える呼び水となり、儒教と共に日本にもたらされた際に、その新しさと高度な体系を有していた事から時の為政者たちにとって、儒教ではなく仏教が国家の支柱として受容されたと読み解いていきます。その上で、葬送儀礼に加われなかった点を指摘して、日本における儒教の限界を指摘します。
国家を動かす王権と鎮魂と冥を司る仏法、仏法の顕現として祀られる神々。日本史の中で描かれた物語、文学たちも多くはこの二つの軸に沿った内容であったことを再確認していきます。
宗教という側面で文学、思想史を語る著者。その結果、著者の歴史的な転機における表現もその影響を強く受けていきます。中世の幕を開ける鎌倉新仏教という表現は今では避けられる傾向にありますが、著者は大仏復興と勧進聖、重源の活動がその幕開けであることを明確に述べ、近世の始まりとしては元和偃武を位置づけていきます。さらに、多くの場合明治維新という表現を添える近代の起点を示す表現には「御一新」の語を繰り返し用い、あくまでも王権と仏法の動きとして時代の推移を綴っていきます。
王権と仏法のバランスが徐々に崩れ始める近世。平時における武家の統治を思想的に支えるために儒教の影響がより大きくなり、庶民の文学へも儒教の影響が見えるようになる点を指摘します。この流れの中で国学の勃興、神道の浮上、その先に尊王攘夷を見出していきますが、著者は起点として復古主義的な荻生徂徠の存在を指摘し、古典解釈の厳密な再検討による読み直しという行為自体が思想面で強い影響を与えたと述べる一方、鬼神論に対しては極めて先進的な唯物論者であった新井白石から逆行する形となる平田篤胤の思想(冥界に関する二元論)と津和野国学による転換がその後の国家神道、皇室の信仰へ強い影響を及ぼしたことを指摘します。儒教の影響が次の時代の萌芽となる一方、葬送儀礼としては儒教形式が幕府により否定された結果、民衆においては葬式檀家として現在にまで繋がる冥の部分、仏教の影響が思想面でも強く残ることを明確にしていきます。
著者による王権と仏法による二つの軸で描かれる思想の歴史。そのような姿は御一新による「神武創業」と太平洋戦争の敗北による「国民の総意」体制によって二度、大きく様変わりしたと述べていきます。中央集権と親和性の高い儒教の思想が持ち込まれた上での天皇を頂点に置く家父長制に倣う国家体制と、それを支える皇室の冥を司る神道と民衆の冥を司る仏教。近代国家としての憲法とその枠組みから逸脱した天皇の存在の危うさの先が近代の軸として語られていきますが、著者の専門分野から離れていくためでしょうか、全体の著述はやや雑多に綴られる近代史へと移り変わっていきます。
流石に近代史の範疇になると数多くの人物がキーワード的に綴られていきますが、冒頭の著述からすると拍子抜けするほど淡白な近代の思想を語る部分。そして、近代から現代に至り、著者が描いてきた思想の枠組みがほぼ潰えたその後(天皇の行動「象徴としての勤め」を国民の総意という形で追従的に容認し蓄積されていく過程と戦後体制による表層的な国民主権の推移を小伝統と称する)を描く段になると、その想いは自らの研究者としての歩みを投影するようになります。
戦後の学制改革を以て、大学がエリート養成機関からテクノクラート養成へと転換したことによって、「文豪」そして知識人という存在が生まれることがなくなった、その結果が現在に続く思想としての日本の低迷の発端であることを濃厚に漂わせて、道筋なき現代の姿と、改めて日本に視点を据えた思想史を過去に遡って丁寧に掘り起こしていく必要性を述べていきます。
新書という限られたフォーマットの中で綴られる、著者がこの数年来積極的に上梓されてきた著作群の交差点となる、次へ進むためのキーワードを整理し、再確認するための一冊。
新書という誰でも手軽に読むことができるフォーマットでありながら、素手で触るとちょっと火傷しそうなくらい極限まで絞り込まれた内容故に読む方をかなり選ぶ一冊ですが、著者が囁く指摘に耳を傾けながら、自らの持っている歴史的な理解を見つめなおすと、その中に織り込まれた、思想としての日本史の姿がほんの少し見えてくるようです。
他社さんの書籍で申し訳ないのですが、通巻300冊を達成した人物叢書の販促史料にある、登場人物別の教科書採用率。
じつは、近代以前においても文人、僧侶の登場人物はかなり多いのですが、教科書採用率が極めて低いことが判ります。多くの方々の歴史的な知識の下敷きとなる教科書の記述を考慮すると、著者の懸念、危機感と本書の位置づけが見えてくるようです。
