近年続々と刊行される日本史、中世史を扱った書籍たち。
歴史書籍を得意としている版元から刊行される作品を追いかけるだけでも、結構大変(時間はもちろん、お財布を含めて…)なのですが、新書や文庫からもどんどんと新刊が送り込まれてくるので、どれから読もうか困ってしまう時も珍しくはありません。
そんな選ぶのに困るぐらいの今月刊行された日本史関係を扱った新刊で、全くのノーマークだった、珍しい組み合わせの主人公を扱った一冊をご紹介です。
 「源頼政と木曽義仲」(永井晋 中公新書)です。
「源頼政と木曽義仲」(永井晋 中公新書)です。
著者は長く県立金沢文庫に所属されていた、中世史の研究者。金沢文庫に関係の深い、鎌倉北条氏に関する多数の著作を書かれています。そのような著者が今回手掛けるのは、鎌倉幕府成立の前駆となる源平合戦(本書では、一般的に親しみやすい、こちらの用語を一貫して用いています)。そして、前半のメインに扱うのは同じ源氏でも最もメジャーな河内源氏ではなく、敢えて摂津源氏、歌人で大内守護でも知られる源頼政を据えています。更に物語後半、源頼政が敗死した後を引き継いで描かれるのは、河内源氏でも敗者の立場となる木曽義仲。
この二人に何の繋がりがあるのか、お判りになる方であれば納得かと思いますが、その繋がりの要に存在するのが、二条天皇の系譜を継ぐ八条院とその家族、近臣たち。そして、この物語を生み出す駆動力となる以仁王の存在。
本書は近衛天皇の崩御から木曽義仲の敗死までという、この種の本としては珍しい時間軸で、その間に活躍する二人の主人公の動きを描いていきますが、両者の直接的な関わりが描かれる訳ではありません。また、両者の人物史を描くようにも見えますが、どちらかというと、平家物語(ないしは時代史)の流れの中で彼らを描いていきます。
日本で一番、源頼政の著作を手掛けたとあとがきで語り、ゲームの駒を動かすようにと述べられるほどに、著者にとって手慣れたテーマを描く本書。その筆致は研究者の方が書かれた一般向け書籍としては、ちょっと拍子抜けした感じすら受けます。文中に際立った議論のポイントを設けず、深堀する訳でもスルーする訳でもなく、漏れなく淡々と描かれる時代背景、権力闘争のエスケープゾーンとしての八条院に集う人々とその要点を述べる著述。大内守護として、そして武家源氏、平氏並立の要求に応える頼政の立ち位置への言及。そこには、自らの研究成果を全面に打ち立てたり、他の研究者の見解に対しての反論を明確に述べる事もない、拘った展開すら持ち込む事もなく、読み物に徹した淡泊とも思える筆致に終始します。
平家や王家(鳥羽、崇徳、後白河)、そして河内源氏を中核に描く平家物語を解説した類書とは一線を画す、微熱な筆致で描かれる、八条院に集う人々を軸に描く、もう一つの平家物語。そこには、平家物語を読み本系と語り本系に分けて著述を比較したり、登場人物たちの心象から物語を描こうとする、歴史研究家の方が書かれる書籍とは少し違った、文芸作品を思わせる雰囲気すら感じさせます。
著者のその想いが色濃く感じられるのが、前半の主人公である源頼政の蜂起の理由と、そこに至った想いを綴る段。唯一、他の研究者の見解に直接言及する、以仁王の挙兵理由自体が、誰にとっても挙兵、討伐する理由がなく、単に八条院周囲に皇統として担ぎ出される事だけを排除する意図しかなかったとみなしながらも、結果的に流れによって(この辺りの解釈は殆ど文学的)蜂起に与した、従三位という空前の位階を得ながら、大内守護という、武人として二流の立ち位置であった、源頼政の空しさへの想いを切々と述べていきます。
その著述には、当時の摂津源氏が河内源氏より圧倒的な勢力を有していた事(頼朝が流されていた伊豆国自体、彼の知行国)を示す一方、どんな煌びやかな立ち位置にあっても、滅びの時がやって来るという、平家物語自体が描く、無常感を漂わせていきます。
その想いが更に強まって来るのが、木曽義仲を描く後半。平治の乱によって瓦解した各地の源氏勢力を掻き集めながら上洛を果たした義仲の勢力。類書にある様な、一方的に田舎者の烏合の衆と蔑むのではなく、中核は少数の勢力ながら良く錬られて、主従の固い絆で結ばれた東国武将たちという、ちょっと古めのステレオタイプで描いていきます。義仲自身も、京に上った後は田舎者であることを逆手に取った立ち回りを演じられるほど知略に優れていた事を紹介する一方、玉であった北陸宮一行を一緒に連れずに入京し、処世術に長けた後白河の近臣たち(ここで後白河を評して、彼らのような政治向きの近臣は簡単に切り捨てるが、財務等を預かる官吏たちを大事にした事から、信西と同じく強い国家観を有していたと指摘します)と渡り合える近臣が決定的に不足していた事を明確に評していきます(そのような弱点を、いいように行家に弄ばれることになるのですが)。
京に入ってから孤立感を深める義仲とその郎党たち。その最後は、源頼政が以仁王に仕掛けられた運命に巻き込まれる形で自ら滅亡の道に突き進んでしまったように、頼朝と後白河によって仕掛けられた窮鼠と化す命運に呑みこまれるように滅亡の道を突き進んでいく事になります。最後の最後まで力戦を続ける義仲主従。平家物語の描写を借りながら滅びの美学とまで述べるその筆致には、時に歴史小説を思わせる語りが添えられていきます。そして、後継者に次々と先立たれる八条院と、大姫の悲劇に繋がる終章に描かれる、所縁の者たちのその後の物語も、頼政の段と同様に無常観を強く感じさせる結末を綴っていきます。
極めて読みやすい手慣れた筆致で描かれる、歴史物語として綴られた八条院という第三局を軸にした新たな視点による平家物語。そこには、平家物語に通底する想いそのままに、著者の歴史に対する儚い想いが淡く映し出されているかのようです。
<おまけ>
本ページより、関連する書籍のご紹介。
- 今月の読本「頼朝がひらいた中世」(河内祥輔 ちくま学芸文庫)推理小説と歴史の駆動力
- 本文中、唯一言及される研究者の方が書かれた、同時期の時代史を全く逆のアプローチ(平家物語を戦記として否定的に捉え、他の史料を重視する。主に王朝国家側の視点から、王朝国家を再興する一翼としての武家、頼朝を位置づける)で描く一冊は、奇妙なことに、本書と極めて似通った読後感を読者に感じさせるかもしれません
- 今月の読本「動乱の東国史2東国武士団と鎌倉幕府」(高橋一樹 吉川弘文館)南北交通開拓を目指す幕府と移動する武士たちの交流史
- 今月の読本「院政とは何だったか」(岡野友彦 PHP新書)題名に見る相克できない著者の意図
- 今月の読本「三浦一族の中世」(高橋秀樹 吉川弘文館)通史としての中世史から三浦一族への交点を結んで
- 今月の読本「熊谷直実 中世武士の生き方」(高橋修 吉川弘文館)郷土の豪勇への熱い眼差し
- 今月の読本「武蔵武士団」(関幸彦編 吉川弘文館)軍記と系図、街道が織りなす武士達のオムニバスストーリー

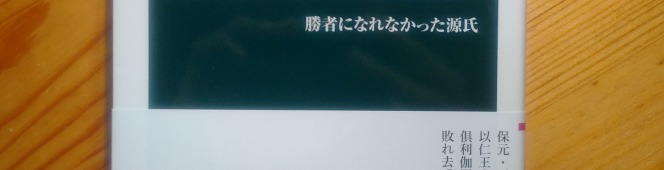

コメントを投稿するにはログインしてください。