吉川弘文館さんが日本歴史学会からの委託を受けて刊行を続ける、終わらないシリーズとも評される一大人物伝のシリーズである「人物叢書」。刊行以来、幾度となく絶版となった作品を復刻していますが、昨年はSNSを利用されている方を含めて、広範な読者の方にアンケートを取っての復刊キャンペーンが実施されました。
何時もの如く、悪乗りで何冊かの復刻をリクエストしたのですが、嬉しい事に、推させて頂いた何冊かが今回、復刊を果たすことになりました。
リクエストして復刊して頂いた以上は、何時かは購入しなければ申し訳が立たないという訳で、漸く山を下りた年末に、まずは一冊購入してきた本をご紹介します(復刻版をずらり取り揃えて下さっていた、ジュンク堂書店甲府岡島店様に今回は感謝です。河村瑞賢と随分悩んだんですよ、実は)。
年末年始にコツコツと読み続けていた、今年最初の一冊、「人物叢書 月照」(友松圓諦 吉川弘文館)をご紹介いたします。
本書は昭和36年に初版が刊行され、昭和63年に改められた版が元になっていますが、旧版のまま復刻されたのでしょうか、少々古風な活字で刷られています。また、近年刊行される書籍ばかり読んでいる身には、古風な文語体を読みこなすのに少々骨が折れた事を正直に述べておきます(文章自体は極めて平明です)。
しかしながら本書が極めて貴重でかつ、現在に於いても読むに値する価値があるのは、ほとんどの場合において西郷隆盛の添え物として扱われる月照自身の、現時点における殆ど唯一の評伝であることです。
西郷と肝を照らし合わせて、京都に於ける公家と武家の橋渡しをした、尊皇派で憂国の志士のような、ややもすれば不良僧、破戒僧とも見做されそうな人物が男二人で悲劇的な入水、といったイメージを全面に語られる場合が多いのですが、本書をお読みになれば、そのようなイメージが全く異なっている事に気が付かれるはずです。
京都を代表する寺院である清水寺の塔頭にして、実質的な寺務を統括する成就院の第24世本願という、当時の京都に於ける仏教界でも高位に位置する僧侶。奈良興福寺の一乗院に連なる法相宗としての律に依拠する厳しい側面。弟である、のちに25世となる信海は長く高野山に学僧として留まっており、その弟の研鑽に自らは及ばないと素直に評する、教学を追求したいと願う想い。全く正反対の、病弱ながらも、師である蔵海から続く、山内における激しい抗争の収拾と、一山の復興を背負うことになる、世俗に塗れる苦しい心境。観音信仰を母体とする清水寺が培ってきた信仰心が生み出す、渡世に寄り添う大乗律への想い。
藩主斉彬の使いとして、その名を雄藩に響かせ始めていた西郷とはいえ、およそ不釣り合いな、一山を代表する三職のうち二職をも兼掌した、清水寺の最高位にあった月照との関係。
実は、西郷と月照がどのような関係にあったのか、最晩年となる密勅を水戸に下す段階から薩摩への下向に至る時点以前に於いて、記録上で知られている事は殆ど無い点を明示します。西郷が斉彬の下で活動していた時期、本坊である成就院は弟である信海が継いでおり、本人は京都周辺の寺院や空屋敷を転々としており、空想好きな方であれば、同志を募り、内偵を恐れて、居所を転々としていたと想像の羽を広げたくなるかもしれません。しかしながら、彼が成就院を退去したのは、前述の山内の抗争と本山である南都の一乗院による意向の板挟みあった末に、隠居届を出し続けた上での善光寺への無断出奔に対する懲罰としての域外隠居としての退去であったことを明示します(後に許されますが、入山自体の差し止めはされていなかったこともあり、その後も成就院に弟を度々訪れます)。
そして、月照を悩ませ続けたこの問題の解決に助力したのが、本山である一乗院宮の弟子であり、後に青蓮院宮となる、中川宮。そして、興福寺に強い影響力を持つ、清水寺を祈祷寺としていた、歌道を通じても交流のあった摂家筆頭、近衛家との繋がりが浮かび上がる事になります。両家に出入りする公家、宗教関係者たち、さらには近衛家と縁戚で繋がる薩摩との関係から、当主である近衛忠煕の使僧としての役割を務めるようになった事を見出していきます。
著者は、勤王運動に関わった人々との関係を綴る章の冒頭で次のように綴ります。
「彼は決して主謀者ではない。たまたま、そうした主謀者と長く交際していたので、自然、その中にひきずりこまれたという方が正しいかもしれない。ただ彼の身分が当時として重要な役割をしたというだけのことである」
勤皇の志士をイメージされる方にとっては失望を感じるかもしれない一文ですが、その後に続く内容を読んでいくと、肯定せざるを得ないようです。公武の交流が大きく規制される中で自由にその双方を行き来する事が出来た、藤色衣を纏った高位の祈祷僧にして使僧という立場。志士というイメージとは正反対に見える彼が、なぜそのような活動に没入した上で入水という結末を遂げる事になったのでしょうか。
本書の著者は戦後に神田寺を興された、NHKラジオ法話『法句経講義』でも著名であった方。ヨーロッパ留学も経験され、現在の大正大学で教鞭を執られていた時代もある仏教研究者で、月照自筆の書籍を清水寺から委ねられていたほどに、精神面を含めてその研究を追及されていらっしゃいました。
本書は、そのような月照の仏教者としての生き様を要所に織り込む事でその思想面での変化、素地を見出していこうとしていきます。この辺りの著述になると、相応に宗旨に慣れていないと読み解く事が難しくなる部分ですが、月照の想いを同じ仏教徒としての視点から掬い取っていきます。一山の財政的な危機に直面しても、三職六坊と呼ばれる塔頭毎が勢力争いと続ける姿と、名義継承に立てられる年少の住職(月照自身も)や宮中を模した仮名に見る形式主義に落ちた清水寺、当時の京都に於ける寺社の姿に強い憤りを募らせる著者。印象的に語られる、その中で一人、門前に降りて廻行を行うという、御院主様と称された、三職中で実務を司る(他の二職は主に堂上出身の子弟が務めた)、寺領133石、門前5町を支配地として束ねる本願の責務を果たさんと、病弱を押して臨む月照の姿に、彼が会得したであろう二つの律のうちの小乗律としての戒律を重んじる宗教者としての強い矜持と、大乗律としての摂衆生戒、実践を通して人々に寄り添う宗教者としての生き様を見出していきます。その先に見出す尊王への思想的な展開について、本書では色々な可能性を綴っていますが、その確信と踏んだ子島流の法相密について、著者は門外漢だとして確定的な事は述べられません。
著者の手元にあった2冊の月照直筆の書は東京大空襲によって焼亡して今は無く、それ以前に蓄積していた研究成果と宗教者故に収集できた清水寺に残された彼の行動を記す内容と思想面での深化を併せて綴る本書。それだけでも唯一の内容を具えていますが、刊行後50年以上が経た今でも、その後に続く評伝が無い中で、今を以て貴重な一冊。
テーマ毎に時間軸が巻き戻されて綴られるために、少々追いかけにくい構成ではありますが、幕末の京都を舞台に、実際に活動された人物の息吹とその本質、交流した人々の姿を伝えてくれる、人物伝として相応しい内容を具えた一冊。本書を手に、今年の大河ドラマにおける前半のクライマックスとも言えるシーンでどのように演じられるのか、興味深く観てみたいところです。

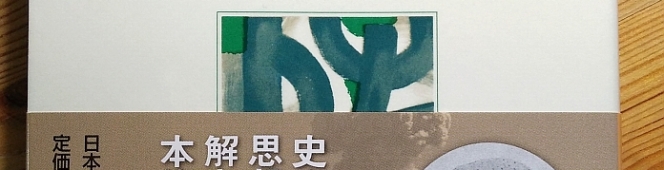

コメントを投稿するにはログインしてください。